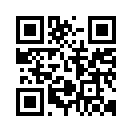聖武天皇をはじめ

都市伝説は、基本的に現代発祥の噂話で、根拠が曖昧であったり不明であるものを言う。
遠い昔から伝わる伝説とは、違う性質のものとして分類される。
昔話の伝説は、場所や年代など特價機票、
すべてにわたってありえないと思える話ばかり。
それに対して、都市伝説は何でもない所から生まれた、
ありえそうな話ばかり。
現代の都市伝説の幾つかを紹介すると、
あるお好み焼き店で、ヒミツの言葉を言うと裏メニューが提供される。
(どんな言葉かは、わからない。とにかくヒミツの言葉。)
また、とあるファーストフードの肉には、ミミズや猫などあやしい肉が使われていて、
そのヒミツを知り、決して口外しないということで、
月々口座に振り込まれている人がいる、など。
こういった話は、噂が一人歩きをしているが、実際には確かめられない話、
半ば、ジョークのようでさえある。
都市伝説の性格に近い話に、「青衣(しょうえ)の女人」というのがある。
これは、奈良のお水取りの行事の中で伝えられる話吸塵機。
古くからある行事だが、今も途切れずに、厳粛に行われている。
お水取りの行事の中で東大寺ゆかりの人物の過去帳が読み上げらる日がある。
その日は、聖武天皇をはじめ、光明皇后、行基、藤原不比等、良弁僧正など、
何千名という人物たちが読み上げられる。
その中に、「青衣の女人」という名が入っているという。
これは、実際の個人の名ではなく、単に、青い衣を纏った女性という意味。
ある年、練行衆が読み上げているときにイリュージョンがあらわれて、
「我をば、読み落としたるぞ」と言って消えたという。
それ以来、読み上げられるようになった、という。
信憑性に関しては、何とも言えない。
明治時代に日本にやってきたフランス人作家ピエール・ロティが著書『秋の日本』に
著している言葉に、
「大仏のお寺(東大寺) は、笑うためのお寺、途方もないジョークに溢れている」
とある郵輪旅行團。
これも伝説と言うよりジョーク?