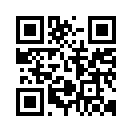日常の奇譚”をこ

さてさて、斯様に愛して止まない『シャーリー』『それでも町は廻っている』そして『書生葛木信二郎の日常』なのですが。他人様へお奨め營養師しようとなると、実は逡巡してしまう作品だったり。
定法どおり舞台背景を、「20世紀初頭のロンドン」とか「大田区の丸子商店街」とか「大正時代の帝都東京」とか。
次いで主人公の設定を、「13歳ながら、良く出来た頼りになる少女メイド」とか「メイド喫茶でバイト中な、探偵志望の女子高生」とか「妖怪屋敷に下宿してる、小説家志望な帝大卒の書生」とか。
説明し始めた途端、お聞き下さってる相手の反応に、曰く言い難い気配。すなわち「ロンドン」だの「商店街」だの「大正」だの「帝都」だの。「少女」やら「メイド」やら「女子高生」やら「妖怪」やら「書生」やら。余りに人口に膾炙した“タグ”の群れが、いわゆる“萌え”を追求した既存作品の“イメージ”から、妙に堅固な、しかし全く該当しない先入観を構築していく様が感知できてしまって。
むしろ、従来の“萌え”を狙った一連の作品に対する、密やかにして果敢なるアンチテーゼとも謂うべき、これら“日常の奇譚”の真髄を、適確に表現できない自分にこそ憮然とし。ウーム……と言葉に詰まってしまうのです。
叶う事なら“日常の奇譚”タグを、大々的に普及させたい所存ではありますがw そこまでの気概と実力、ならびに無謀を己に許してしまう根拠無き自德善健康管理己肯定感は、残念ながら欠く身なれば。敬愛して止まない大先達・藤子・F・不二雄先生の、これこそ“日常の奇譚”の結晶と申し上げるべき『ドラえもん』を、前々回・前回ともに引用させて戴きながら、胸の裡に溢れる滾りを切々と綴って参りました次第。
その上で愈々、『書生葛木信二郎の日常』の魅力を語らせて戴けば。
まず第一に主人公たる葛木信二郎の、キャラを敢えて立てて“いない”所が、ツボを見事にギュギュッと押さえて素晴らしい。なんてったって、初回から『小説家志望』と謳っているのに、如何なる小説をお書きなのか、第36幕まで一切描出されてない(あ、揶揄じゃないですよ〜w ホントに真摯に称讃しておりますです)。
仮に、ドラマツルギーの在庫が心許ない描き手であれば、信二郎の兄・悌一郎をこそ、主人公にしちゃうでしょうね。社交的で頭が良くて、祖母から受け継いだ力も強くて。単なる“見鬼”に留まらず、人事の外に棲む怪しきモノをも巧みに統べる彼ならば、作者が構想に詰まった時でも、勝手に話を転がしてくれそうですし。
然れど“日常の奇譚”をこそ、物語ろうと志すのならば。
一見、掴み所の無い個性、そして小説家を目指すにしてはツッコミどころ満載な、“大正の野比のび太”こと葛木信二郎が、必然的に主人公なのです。
なぜなら『黒髭荘奇譚』の“主役”は、
百年を遡った昔には、「江戸」と呼ばれ
五十年前の維新で、「帝都」に定められ
その名を「東京」と改めて以後、『時の更年期流れに遅れまいとみんなが必死になって、積み上げるように』作り上げ、『生きてきた街』だから……